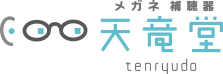「視距離」=「見る距離」について その1 私たちの生活への影響

私たちは日々、何かを「見る」ことで生活しています。朝スマートフォンで時間を確認し、新聞を読み、通勤時に電車の時刻表を見る。職場ではパソコンの画面に向かい、帰宅してからはテレビや読書など、生活のほとんどの場面に「見る」という行為が関係しています。
しかし、「見る」という行為の中でも、私たちは無意識のうちに「距離」を変えて物を見ています。この「見る距離=視距離(シキョリ)」が、実は私たちの目の疲労度や集中力、さらには健康状態にまで影響を与えていることをご存じでしょうか?
本コラムでは、全4回のシリーズを通じて「視距離」をテーマに、多角的な視点から視距離と生活・仕事の関係を掘り下げていきます。初回となる今回は、「見る距離=視距離の基本的な考え方」と「距離ごとに異なる目への負担」「健康や生活への影響」について、幅広くご紹介します。
Contents
視距離(シキョリ)とは何か?
「視距離(シキョリ)」とは、私たちの眼と、視線の対象物との物理的な距離のことを指します。この距離は一見単純に思えますが、視距離によって目の使い方が大きく異なるため、視機能や健康に大きな影響を及ぼします。
眼科や視能訓練の分野では、視距離は「近見(きんけん)」「中間」「遠方(えんぽう)」などに分類され、それぞれで必要な視機能(調節、輻輳、遠見視力など)が異なります。
たとえば、読書をしているときと、車を運転しているときでは、ピントの合わせ方や眼球の動き、眼の筋肉の使い方がまったく違うのです。
視距離の分類
以下に、視距離の代表的な分類とその使用場面をまとめました。

中でも中間距離(60〜100cm)は、現代生活で使われる頻度が非常に高いにも関わらず、老眼の初期症状で最も見えにくくなる距離でもあります。
視距離ごとの視機能の違いと負荷
●近距離の負荷
読書やスマホ操作などの近距離作業では、調節(ピント合わせ)と輻輳(ふくそう:両眼を寄せる動き)を頻繁に使います。この状態が長時間続くと、眼精疲労や肩こり、頭痛の原因になります。
●中間距離の負荷
パソコンや調理、接客業務などで中間距離を見る場合は、調節力を必要としながら、視線を安定させる機能も求められます。安定させるとは、調理中に包丁を見ながら、周辺に気を配れるように視線を固定する状態などです。40代以降で老眼が始まると、最初に影響が出やすいのがこの中間距離です。近視の方の場合、メガネを通して見えるのは遠距離。外して裸眼で見えるのは、近距離です。そのため近距離と遠距離の間である中間距離は、メガネでも裸眼でもピントを合わせづらくなります。
●遠距離の負荷
遠くを見るときは、調節や輻輳の負荷が少なく、目は比較的リラックスした状態になります。ただし、視力が低下していると遠くの対象物を正確に捉えにくくなるため、視力矯正の重要性が高まります。
見る距離が生活に与える健康的影響
●子どもにとっての「視距離」
子どもがスマートフォンやタブレットを使って遊ぶ時間が増えることで、自然と「近距離で長時間見続ける」ことが習慣化しています。これは近視の進行を加速させる要因の一つであるともいわれています。実際に日本では小学生の近視率が年々増加しています。
●大人にとっての「視距離」
大人では、中間距離での見えづらさが生活に大きな影響を与えます。老眼によって「見えそうで見えない」状態がストレスとなり、パフォーマンスの低下や不快感を引き起こすこともあります。特に40代〜50代では、仕事や家庭での中間距離視力の低下が見逃されがちです。
●高齢者にとっての「視距離」
高齢者では、遠距離と中間距離の視力低下が、安全性に直結します。たとえば、道路の段差や信号の確認が難しくなり、転倒や交通事故のリスクが増加します。また、調理時に調味料の表示や火加減が見えづらいといった問題も起こり、生活の質を下げる要因になります。
次回以降の展望
次回からは、室内ワークと屋外ワークごとに「どの距離をどのように使っているか」「その距離を見ることによってどんな問題が起こりやすいか」「どう対処すればいいか」を、より具体的にご紹介していきます。予定しているコラムのテーマは以下のとおりです:
その2 室内ワークと屋外ワークの視距離を比較する
その3 年齢別で1日でどれだけ視距離が変わっている?
その4 職種別の視距離に適したメガネレンズの選び方
まとめ
「視距離」を正しく知ることは、目の健康を守る第一歩です。私たちの生活は、距離によって見え方も使い方も違う“目”に支えられています。日常のちょっとした違和感や疲れを放置せず、自分の「視距離バランス」を見直すことが、快適な毎日への近道になるかもしれません。
この記事はわたしが書きました

齋田祐一(さいたゆういち)
有限会社天竜堂 1級眼鏡作製技能士(旧SSS級認定眼鏡士)
キクチ眼鏡専門学校卒業後、眼鏡の組合で教育事業に関わり、眼鏡店、眼科を経験後有限会社天竜堂へ入社。眼鏡の仕事を多方面から関わることでお客様のお役に立てる商品やサービスの提案に日々邁進しております。